石臼の謎:三輪茂雄
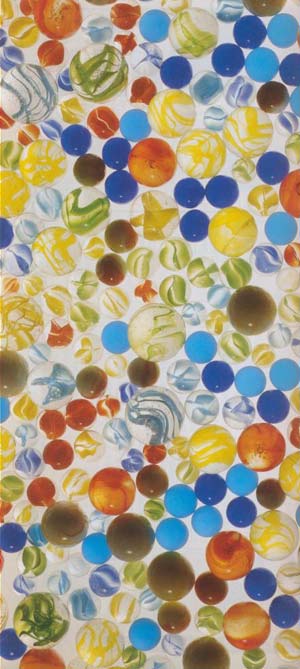
夏の思い出:山本紀之
石臼を回す誰かの手
突然で恐縮ですが、挽き臼、昔話に出てくるおばあさんが挽いている、あのゴリゴリ回るあれってどっちの方向へ挽くかご存知ですか。
近所の農家の隅っこに転がって、そろそろ使われなくなっていたあの、石臼。静かな秋の日を浴びて、うっすら埃をかぶって・・・。これは何だろうと不思議に思ったことを覚えています。
そう、東京オリンピックよりちょっと以前、世の中が忙しくなりはじめた時代です。
ええ、もちろん石臼がもはや機械にとって代わることはできません。
僕たちは「みんな一緒」の味や手触りや、均質な製品を手放せないし、それはそれで価値のあることですから。
ただ「粉体工学」が専門の著者に言わせると「現代の粉砕機は量的な生産力において優っていても、生産物の品質においてはどうしても石臼に追いつけないものがたくさんある」のだそうです。
たとえば抹茶をひくには精度の高いものが必要で、手挽き臼のかわりにさまざまな機械が試されたが、使用に堪えないといいます。
風味や色合いなど人間の官能テストに適うものは作れないのだとか・・・。でも、石臼そのものがその品質を保証するわけではありません。
石臼の目を測り、石臼を回す誰かの手がなければ、僕たちの官能をうつものは生まれてこないのです。
ひとの感じ方に一番合った技術と道具を伝えていくことが――民芸館に陳列されるのではなくて、そして郷愁ではなくて――ひととモノによる創造の本来につながるものなのかもしれません。
臼の挽き方――。例外はあるものの、時計の針と反対の方向に回すのが殆どだそうです。
石臼の謎:三輪茂雄著(クオリ)
軽兵衛